はじめに
「UXデザインの法則 最高のプロダクトサービスを支える心理学」を読みました。
所感
Laws of UXというサイトの作者が著者です。
UXデザインに活用できる心理学がまとめてあります。
本書の最後には技術者倫理についても触れてあるのが、好感を感じました。
今までなんとなくデザインしていていましたが、心理学を知ることで理論的にデザインができそうです1
以下に気になったところをまとめておきます。
- ヤコブの法則
- ユーザーが慣れ親しんだプロダクトと見た目が似ていれば、同じように動くことを期待される
- すでにあるメンタルモデルを活かせば、ユーザーは新たなメンタルモデルの学習なしにタスクに集中でき、ユーザー体験の質が高まる。
- すべてのプロダクトや体験が完全一致していないといけないという意味で提唱しているわけではない。ユーザーが新たな体験を理解するためには過去の経験を活かす必要があるという点を注意喚起している。
- まずは常にありふれたパターンや慣例から始め、その後、うまく行きそうな時だけ慣例から離れるのが良い。
- ChatGPTとGeminiのUIはとても似ています。このあたりはヤコブの法則が当てはまりそうです。
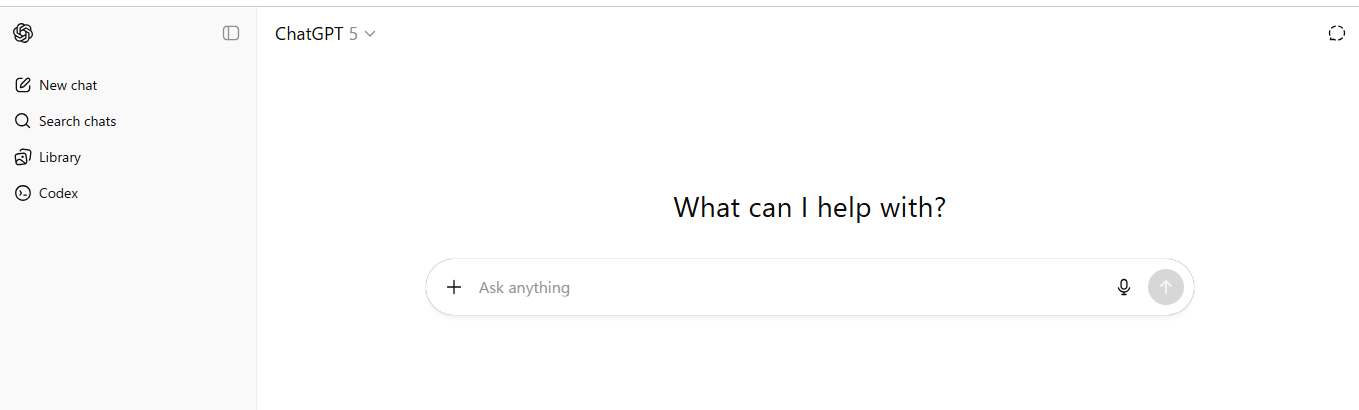

- ChatGPTとGeminiのUIはとても似ています。このあたりはヤコブの法則が当てはまりそうです。
- フィッツの法則
- タッチターゲットには、ユーザーが正確に押せるために十分な大きさが必要。
- 項目同士に適切な感覚を設けることでユーザビリティは向上し、誤ったアクション選択を最小限に抑えられる。
- ヒックの法則
- 意思決定にかかる時間は、とりうる選択肢の数と複雑さで決まる
- 単純化によって抽象的になりすぎると、どんなアクションが実行できるのか、次に何をすればいいのか、どこにどんな情報があるのかがわからなくなってしまう。
- 例えば、アイコンだけのボタンなど。
- ユーザの目標の達成に役に立たない要素を減らし取り除くプロセスが重要
- ミラーの法則
- 普通の人が短期記憶に保持できるのは、7(±2)個まで。
- コンテンツを小さなチャンクに分けることでユーザーがその情報を扱い、理解し、記憶しやすくなる。
- 例:電話番号 0123456789よりは012-3456-789 ほうが読みやすいし理解しやすい。
- ポステルの法則
- ユーザーがとりうるアクションや入力しうる情報すべてに対して理解を示し、柔軟に対応し、寛容であろう。
- ユーザーからの多様な入力を受け入れ、それを要件に合わせて変換し、入力の境界線を定義し、ユーザーに明確なフィードバックを提供する。
- これは半角のみ入力可能なテキストボックスが例にあるかなと思います。最近は全角で入力しても半角に変えてくれるのが多いような気がします。
- ピークエンドの法則
- 経験についての評価は、全体の総和や平均ではなく、ピーク時と終了時にどう感じたかで決まる
- エンドユーザーを喜ばせるためには、プロダクトが最も役立つ瞬間、最も価値がある瞬間、あるいは最も楽しい瞬間を見定めてデザインする
- ポジティブな経験よりもネガティブな経験をより鮮明に思い出す。
- ジャーニーマップ
- ユーザーがどのようにプロダクトを使うかのストーリーを可視化するためのフレームワークです。これでユーザー体験のピークを定性的に分析できそうです。
- 重要な瞬間に細心の注意を払うことで、ユーザーはその体験をポジティブに記憶してくれる。
- 美的ユーザビリティ効果
- 見た目が美しいデザインは、人の脳にポジティブな反応をもたらし、実際の場面でもよく機能すると受け取られる。
- プロダクトやサービスの見た目が美しければ、人は些細なユーザビリティの問題に対して寛容になる。
- Braunの製品はきれいだなと思いました。

- 参照
- Braunの製品はきれいだなと思いました。
- フォン・レストルフ効果
- 似たものが並んでいると、その中で他と異なるものが記憶に残りやすい
- 重要な情報やアクションを視覚的に目立たせる
- 重要なアクションや情報を強調するデザインの意図を伝えたいときや、プロダクトやサービスのユーザーが目的を果たすために必要なものを素早く識別できているかを確かめたいときに役に立つ
- テスラーの法則
- どんなシステムにもそれ以上減らすことのできない複雑さがある。複雑性保存の法則ともいう。
- どんなプロセスも、その核となる部分にはデザインの工夫をもってしても取り除くことのできない複雑性を抱えている。この複雑性による負荷を負うのはシステムかユーザーとなる
- この固有の複雑性をデザインと開発の過程でどうにかしながら、できる限りユーザーの負荷を減らす。
- 例えばEmailだと宛先だけでなく差出人を設定しなければいけないが、現在は自動で埋められている。これはシステムによってユーザーの負荷(差出人の設定)を減らしている。
- ドハティのしきい値
- 応答が0.4秒以内のとき、コンピューターとユーザーの双方がもっとも生産的になる
- 0.4秒以内にフィードバックを行うことで、ユーザーの注意を引き付け、生産性を高める。
- 体感性能を改善し、感じられる待ち時間を減らす。
- アニメーションを入れることで、バックグラウンドで読み込み処理が行われている間もユーザーはつなぎとめられる。
- プログレスバーは正確であってもなくても待ち時間へのいらだちを和らげる。
- 体感性能を改善するテクニック
- 楽観的UI
- 処理が完了してフィードバックを返すのではなく、処理が進んでいる最中にアクションが成功したとという楽観的なフィードバックを提示する手法。
- 楽観的UI
- 適切なフィードバックを提供し、体感性能を高め、プログレスバーを利用することで「待っている」という感覚を全体として減らすことが重要である。
- ユーザーの注意を目前のタスクに引き付けておけるのは10秒が限界と言われている。これを超えるとユーザーは待っている間にほかのタスクに取り掛かりたくなってしまう。
- 10秒を超える場合は、プログレスバーだけでなく、完了までの予想時間や進行中の表記も加える。
終わりに
心理学を知ってから、色々なサイトを見るとまた違った見方ができるので面白いなと思いました。
デザインはセンスと呼ばれたりしますが、ある一定のレベルまでは底上げしてくれそうな知識が多かったです。 ↩︎